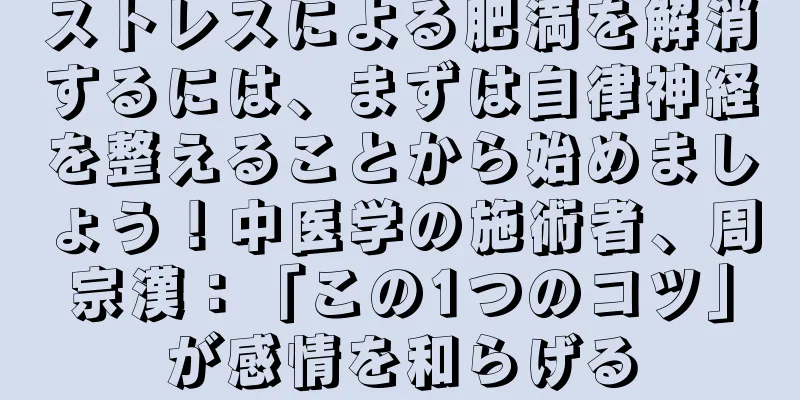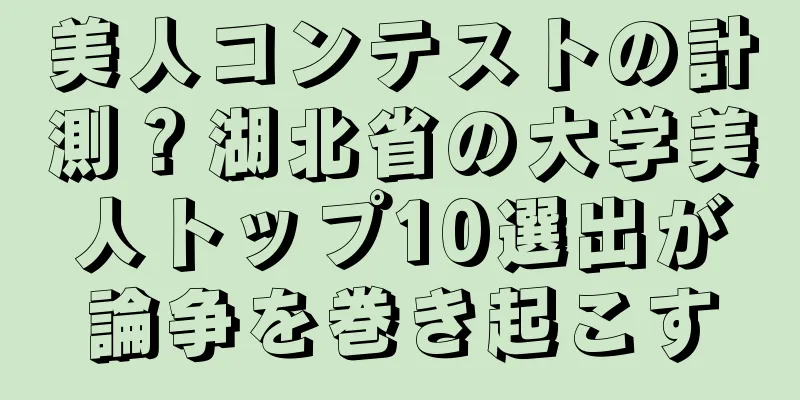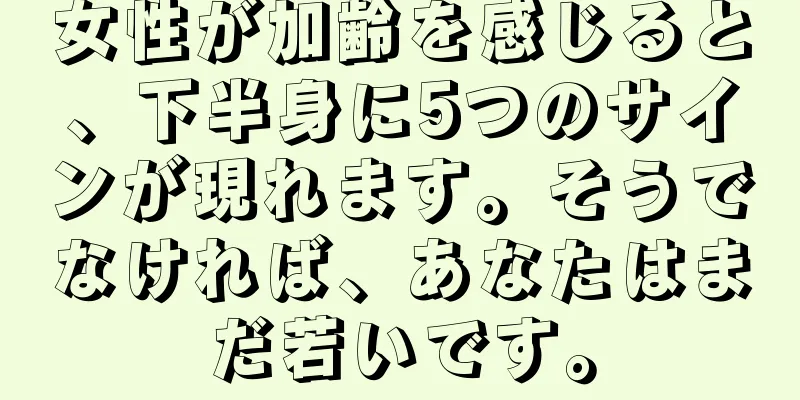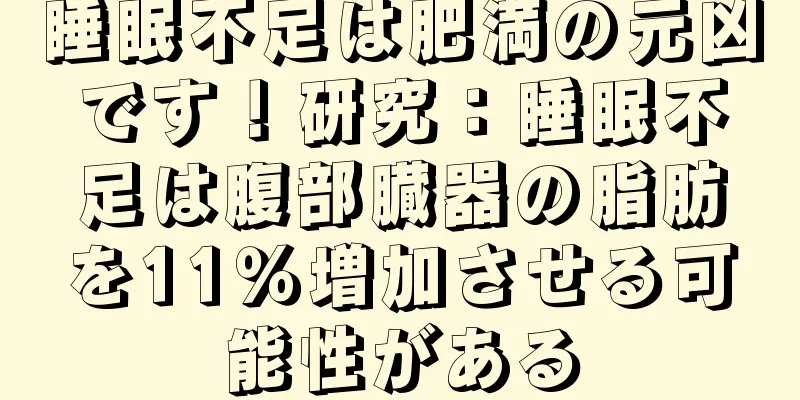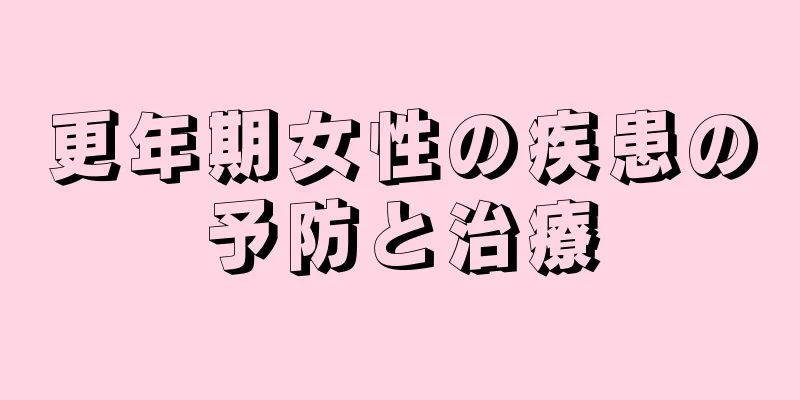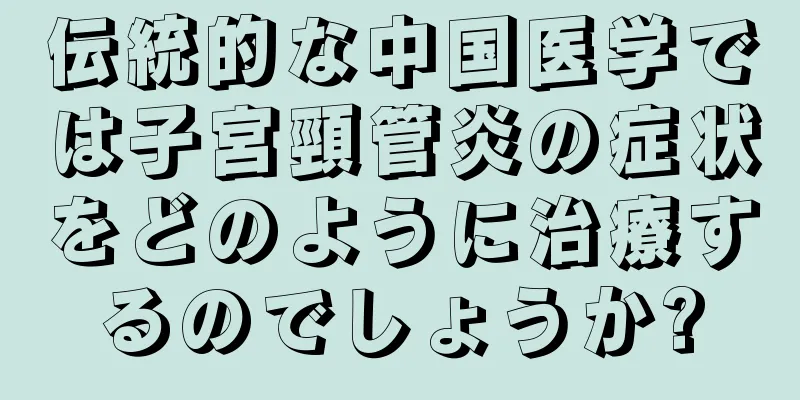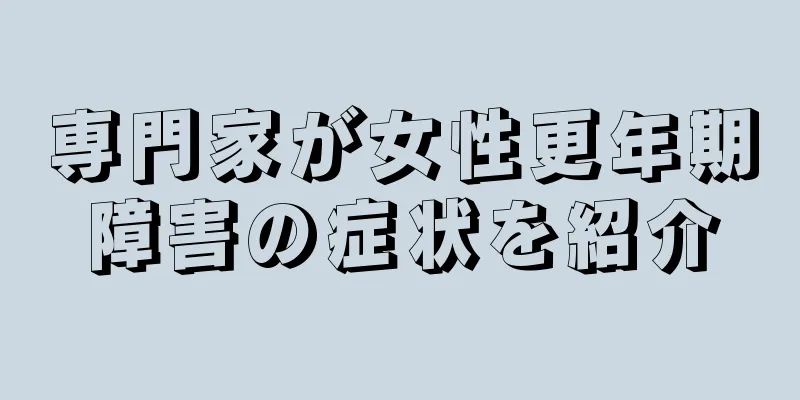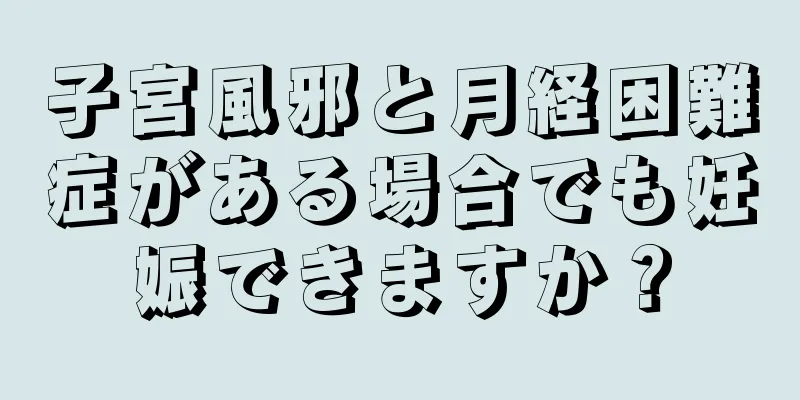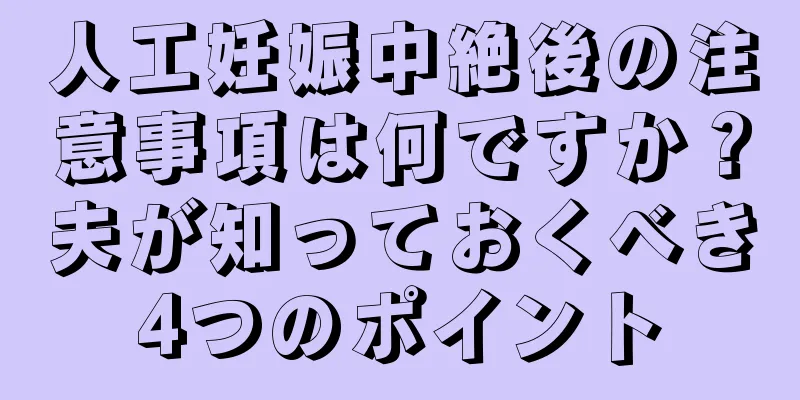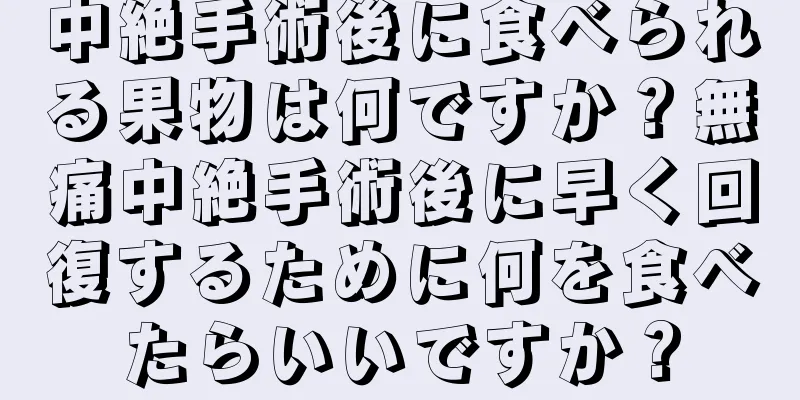痛みのない中絶のための重要な食事のヒントを専門家が解説
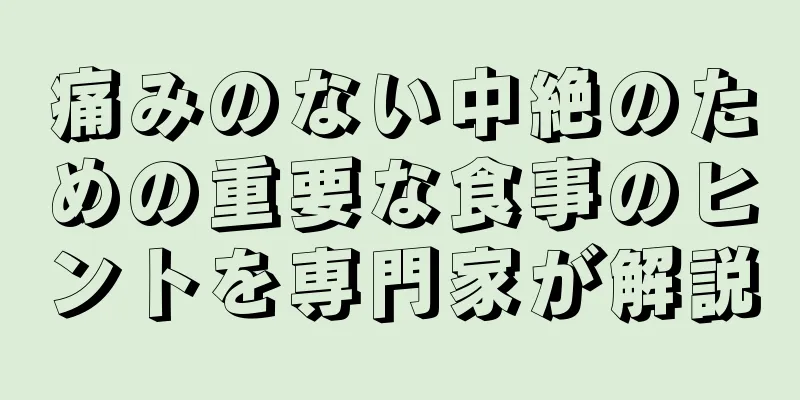
|
無痛中絶の過程は臨床的にはほとんど痛みがありませんが、それでも子供の中絶であるため、女性の友人にはまだいくらかの害があります。積極的な回復が必要ですが、その中で最も重要なのは食事です。では、無痛中絶後の一般的な食事に関するヒントは何でしょうか?ここでは、無痛中絶後の一般的な食事に関するヒントについてお話します。 一般的に、無痛中絶後の一般的な食事のポイントは次のとおりです。 痛みのない中絶の後、女性の友人は新鮮な野菜や果物だけでなく、より栄養価の高い食べ物を食べるべきです。中絶後半月以内に、鶏肉、赤身の豚肉、卵、牛乳、豆類、豆製品をもっと食べるようにしてください。また、流産後の貧血を防ぐために、十分な鉄分補給も必要です。無痛中絶後の回復に適切な期間は半月です。普段から体力が弱っている方、体調が優れない方、出血量が多い方などには、回復期間を適宜延長することも可能です。 無痛中絶後には食べられない食べ物がいくつかあります。例えば、果物:大根、サンザシ、ゴーヤ、オレンジなど、気を整え、血液循環を促進し、冷たい性質を持つ食べ物は食べないでください。痛みのない中絶の後は、より消化しやすい食べ物を摂取する必要があります。刺激のある食べ物(唐辛子、ワイン、酢、コショウ、生姜など)を避け、脂っこい食べ物や冷たい食べ物は食べないか控えてください。これらの食べ物は性器の充血を刺激する可能性があります。カニ、カタツムリ、ハマグリなどの冷たい食べ物は食べないでください。 上記は無痛中絶後の一般的な食事のポイントです。誰もがこのことについてある程度理解していると思います。女性の友人は、無痛中絶を受けた後、できるだけ早く健康を回復するために食生活に注意する必要があります。 |
推薦する
食べる量を減らして運動量を増やしても、太ったままです! 80%の症例はホルモンの不均衡によって引き起こされます
どれだけ頑張って減量しても、体重は高いままですか? 「食べる量を減らして運動量を増やす」は減量の黄金...
侵食面の深さによる頸部侵食の分類
子宮頸部びらんは病気ではなく、慢性子宮頸管炎の症状です。現在、西洋では「子宮頸部びらん」という用語は...
赤ちゃんがまだ授乳中の場合、中絶することはできますか?中絶に関して避けるべき誤解は何ですか?
多くの妊婦は出産後すぐに再び妊娠します。授乳中に妊娠してしまったらどうすればいいですか?中絶できます...
中絶手術前の準備
人工妊娠中絶を繰り返すと、その後の妊娠に影響を及ぼす可能性があります。術後の合併症やその後の妊娠への...
細菌性膣炎の外科治療にはどれくらいの費用がかかりますか?
細菌性膣炎は、女性に多くみられる婦人科疾患として、ますます一般的になりつつあります。細菌性膣炎は、適...
女性の子宮外妊娠に対する看護対策の紹介
どの家族も健康な子どもを望みますが、子宮外妊娠が起こると家族全体の調和が崩れてしまいます。子宮外妊娠...
女性の月経不順の原因はこれらに関連している
月経不順は、すべての人の健康を脅かすだけでなく、精神的苦痛も引き起こすため、誰もがこの病気を正しく理...
無痛中絶手術はどのように行われますか?
無痛中絶には、新しい安全で効果的な静脈内全身麻酔薬が使用されます。この薬は経験豊富な麻酔科医によって...
子宮外妊娠初期の明らかな臨床症状
子宮外妊娠の害は非常に深刻であるため、子宮外妊娠の症状は早期に発見し、早期に治療する必要があります。...
バルトリン腺炎の局所治療薬
バルトリン腺炎の初期段階では、症状が軽度であれば、通常はエリスロマイシン軟膏などの局所薬で治療できま...
右卵巣嚢胞をどうやって取り除くことができますか?何の薬を飲めばいいですか?
右卵巣嚢胞を除去するための治療には、薬物療法、手術、生活習慣の介入などがあり、嚢胞の種類、大きさ、症...
子宮内膜症の症状は何ですか?
子宮内膜症は婦人科疾患です。子宮内膜症はゆっくりとした回復過程を必要とします。子宮内膜症の患者の食事...
チョコレート嚢胞の原因は何ですか?
通常、女性の子宮内膜は子宮腔内で成長します。毎月月経が来ると、毛は抜け落ち、その後再び太くなり、成長...
専門家が女性が子宮頸部肥大を予防する方法を詳しく説明
ほとんどの女性は子宮頸部肥大の予防法を知っているはずですが、子宮頸部肥大の予防法についてどれだけ知っ...
高プロラクチン血症の標準化された診断
高プロラクチン血症と言えば、多くの友人はあまり驚かないでしょう。実際、近年、高プロラクチン血症は一般...