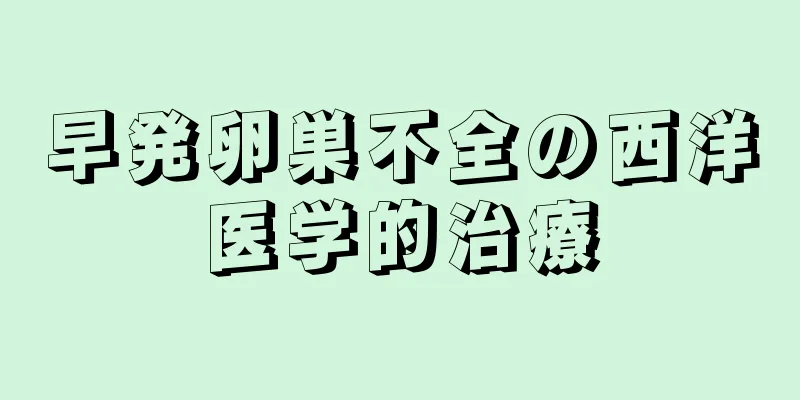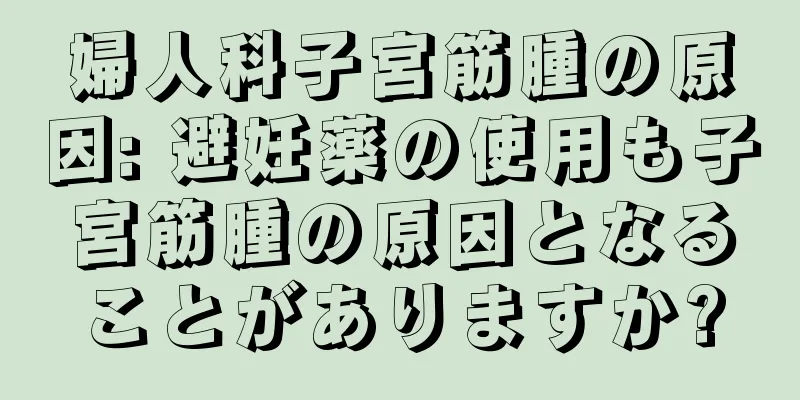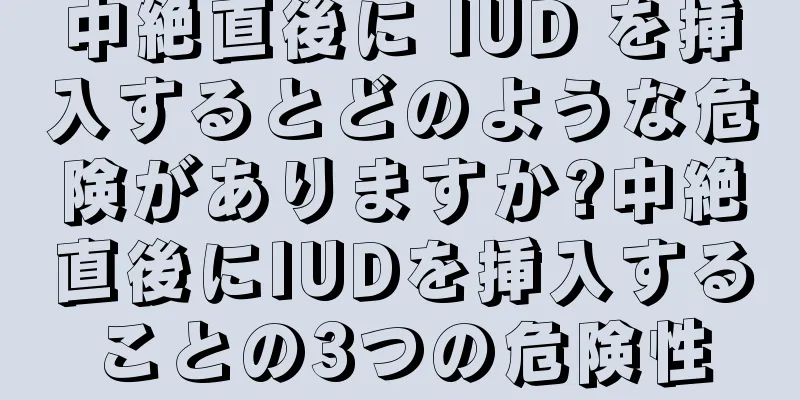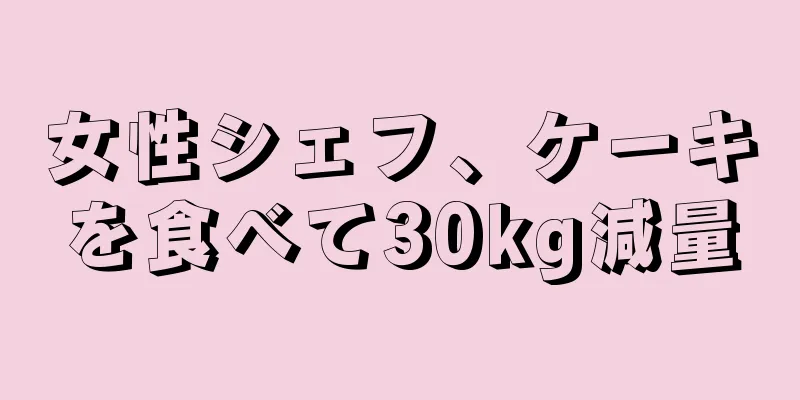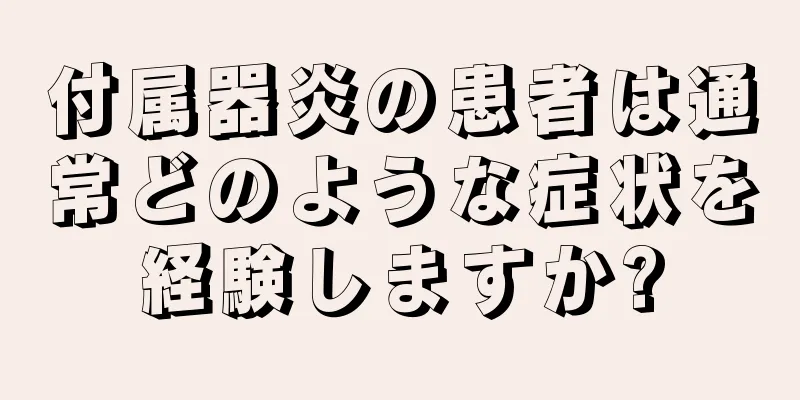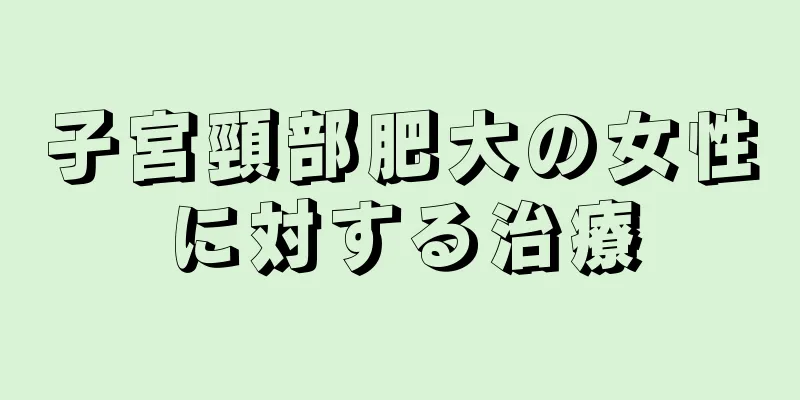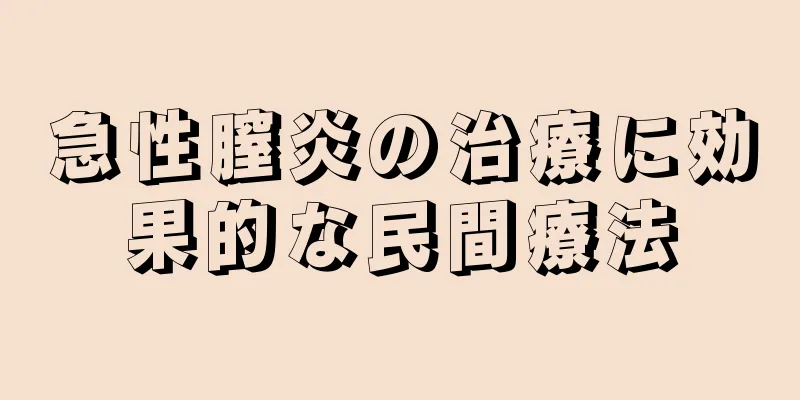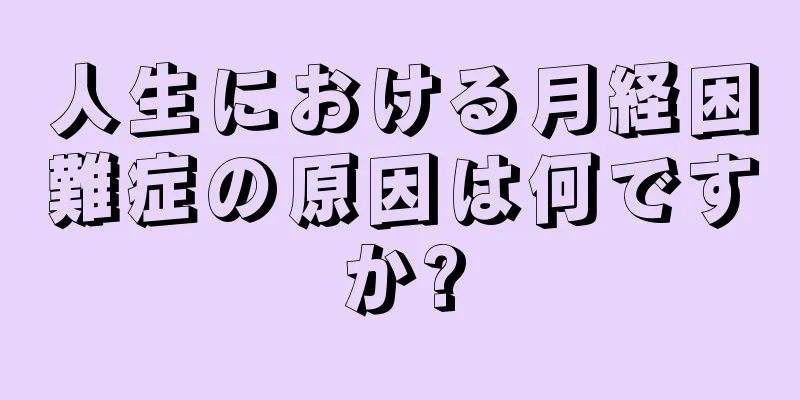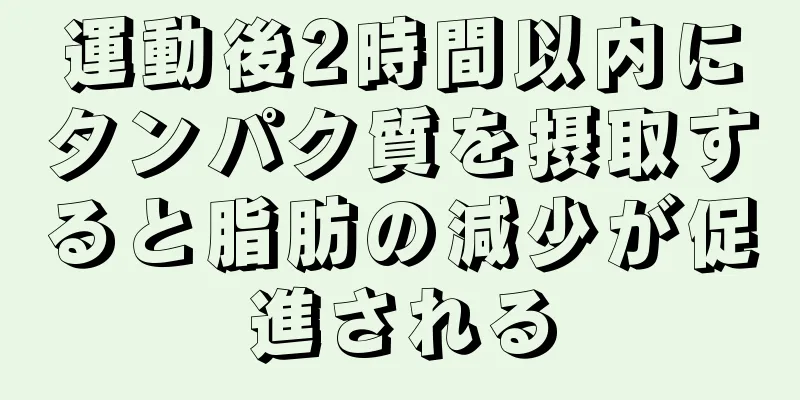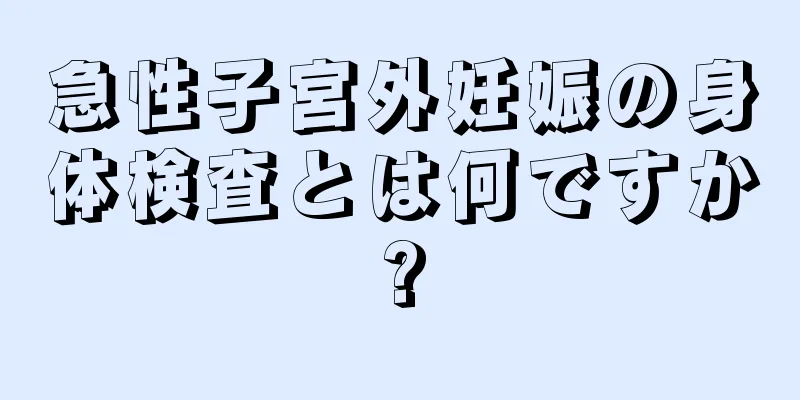女性は日常生活の中で子宮外妊娠の予防策を講じるべきである
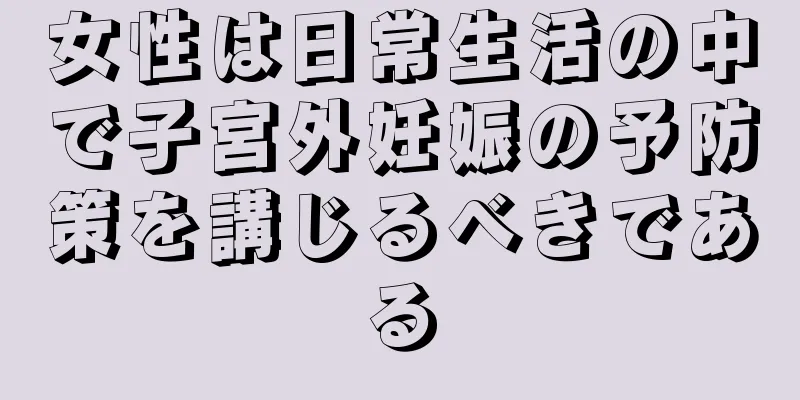
|
女性は子宮外妊娠についてよく知っておく必要があります。この病気は私たちの生活に常に現れ、女性の生活に大きな影響を与えます。女性がこの病気にかからないようにするためには、私たちは生活の中で子宮外妊娠に対するさまざまな予防策を講じなければなりません。以下では子宮外妊娠の予防策について学びましょう。 妊娠と適切な避妊のためには、双方の気分と体調が良い時期を選んで妊娠しましょう。当面母親になるつもりがないのであれば、避妊対策をしっかり講じる必要があります。適切な避妊は子宮外妊娠の発生を根本的に防ぎます。したがって、これは子宮外妊娠を予防する方法の一つです。 生殖器系疾患のタイムリーな治療。炎症が子宮外妊娠の原因です。人工妊娠中絶などの子宮内処置は、炎症や子宮内膜が卵管に入る可能性を高め、卵管の癒着や狭窄を引き起こし、子宮外妊娠の可能性を高めます。子宮筋腫や子宮内膜症などの生殖器系の病気も、卵管の形態や機能に変化をもたらす可能性があります。これらの病気を適時に治療することで子宮外妊娠の発生を減らすことができます。これらは子宮外妊娠の予防においてさらに注意を払う必要があります。 子宮外妊娠を予防するには、月経、出産、産後の期間の衛生にも注意を払い、生殖器系の感染を防ぐ必要があります。すでに病気が発生している場合は、すぐに病院に行き、点滴と輸血を行い、すぐに開腹手術を行う必要があります。 女性が人生において子宮外妊娠を予防するためにこれらの方法に従えば、病気の悩みから解放されるので、女性は上記の記事の紹介に注意を払うべきです。女性は上記の知識を学んだ後、子宮外妊娠についてよりよく理解するべきだと思います。 |
>>: 流産を繰り返す女性は子宮外妊娠になる可能性が高くなる
推薦する
骨盤内炎症性疾患の検査方法
骨盤内炎症性疾患の検査方法は?骨盤内炎症性疾患は通常、下腹部の痛み、下腹部の不快感、時には肛門のガス...
人工妊娠中絶後の不妊の3つの理由
人工妊娠中絶とは、妊娠10週以内の妊娠初期に人工的な方法を用いて妊娠を中絶する外科手術を指します。主...
付属器炎の主な原因は何ですか?
女性が付属器炎を患うと、多くの婦人科疾患を発症することが多いです。したがって、付属器炎にかかったら、...
閉経前補助内分泌療法の選択肢
閉経前補助内分泌療法では何を選択すべきでしょうか?女性は仕事のプレッシャーや不規則な生活により早期閉...
子宮外妊娠の場合、腹腔鏡手術は可能ですか?効果はより良くなる
現在、子宮外妊娠の発生率は非常に高くなっています。原因は様々で、治療法も様々です。腹腔鏡手術で治療で...
頸部イボの患者に適した食品は何ですか?
子宮頸部のイボは、現在では治療が困難です。頸部いぼを治療する場合、頸部いぼの食事療法に注意する必要が...
バルトリン腺炎の患者に対する看護方法は何ですか?
バルトリン腺炎の原因は多くの要因に関連しています。 Youwenbida.comの専門家は、バルトリ...
氷を食べると下痢になる?サルモネラ菌が検出されました!栄養士李一華:サルモネラ菌感染を防ぐ4つの原則
最近、20人以上が高雄のアイスクリームショップにアイスクリームを食べに行ったところ、嘔吐や下痢の症状...
子宮頸部びらんのマイクロ波治療には全身麻酔が必要ですか?
子宮頸部びらんのマイクロ波治療には全身麻酔が必要ですか? 1. 子宮頸部びらんは、一般的に子宮頸部の...
潔白を証明しろ!農業評議会:養豚農家の97%が誓約書に署名
豚肉からクレンブテロールが検出されたため、農業評議会はすべての養豚農家に対し、今後はクレンブテロール...
妊娠中に高プロラクチン血症が発見される
女性における高プロラクチン血症の治療に関する注意事項。女性の高プロラクチン血症の治療に関する注意事項...
長期の腰痛は骨盤内炎症性疾患によって引き起こされます
エイミーは40歳です。彼女は過去2年間、下腹部の膨満感と痛みを頻繁に感じていました。腰がひどく痛み、...
流産後の出血は多い方が良いですか、それとも少ない方が良いですか?流産後の出血のケア方法
早期中絶は避妊失敗に対する一般的な治療法です。胎児がまだ比較的小さく、子宮が大きくなく、胎盤がまだ形...
子宮嚢胞は深刻な病気ですか?何が危険ですか?ここ2日間、出血がありました。
子宮嚢胞は一般的に深刻なものではありませんが、異常な出血を伴う場合は、原因を特定するためにできるだけ...
子宮腺筋症の看護対策と症状は何ですか?
子宮腺筋症の看護対策と症状は?子宮腺筋症の看護対策は主に日常生活における食生活の調整です。 1. 子...