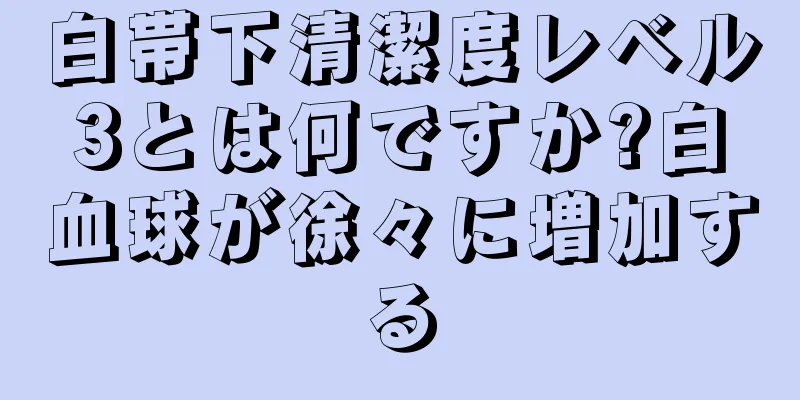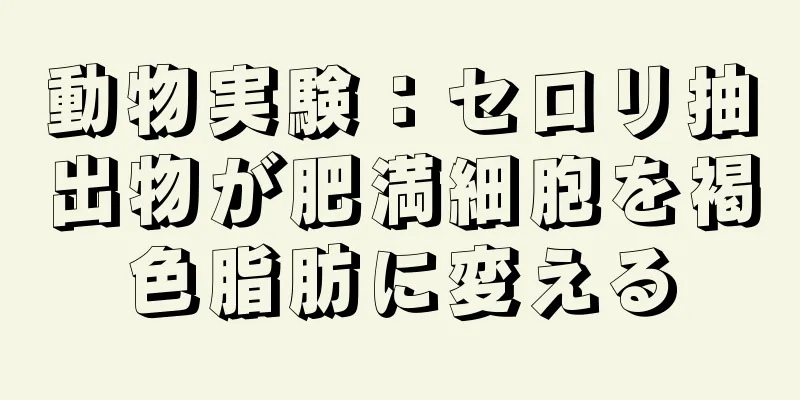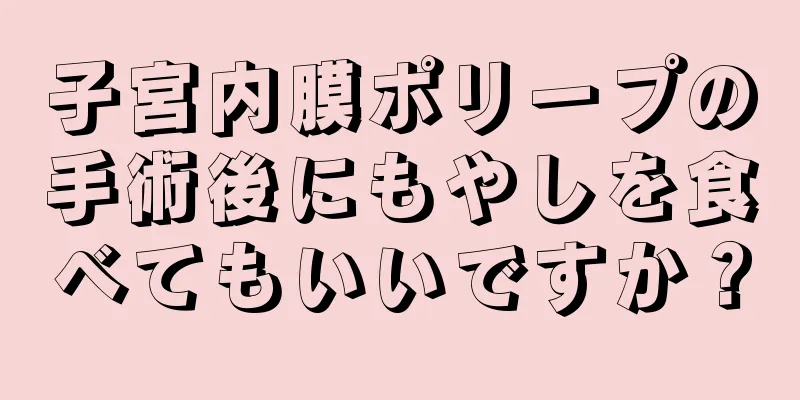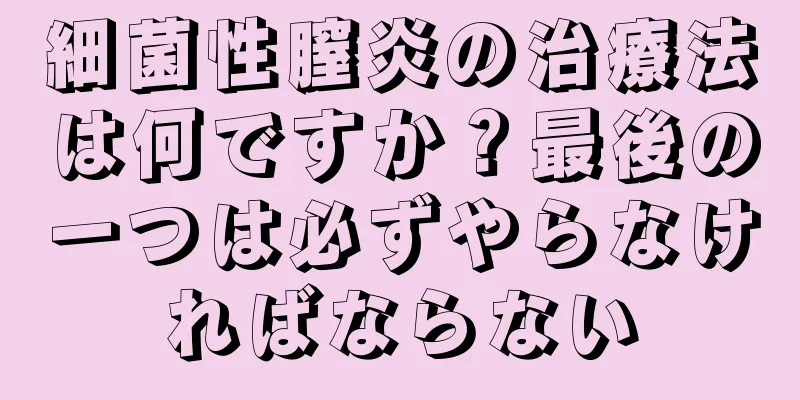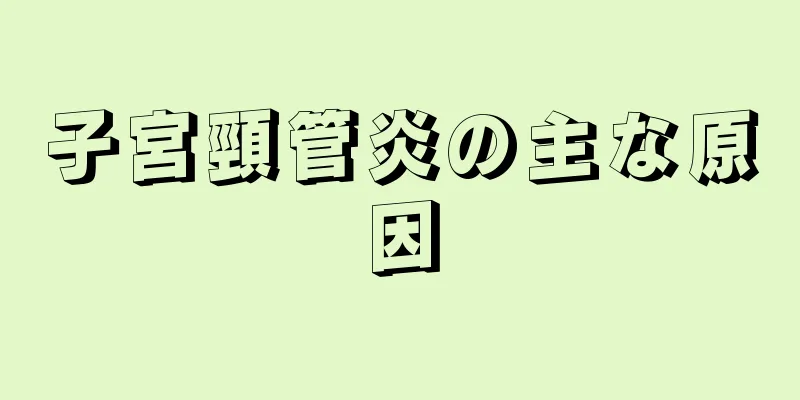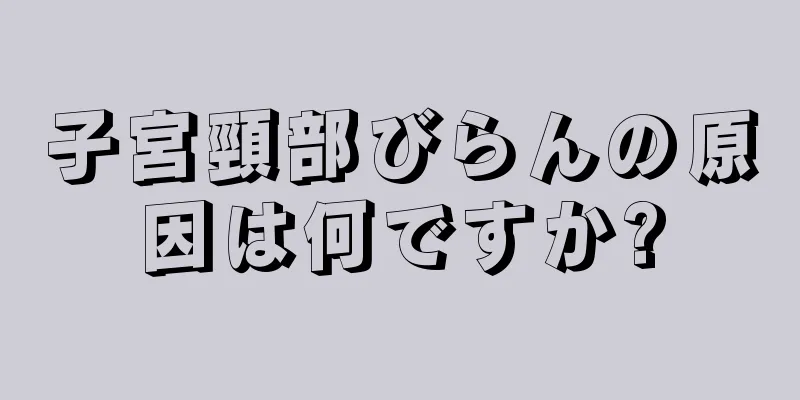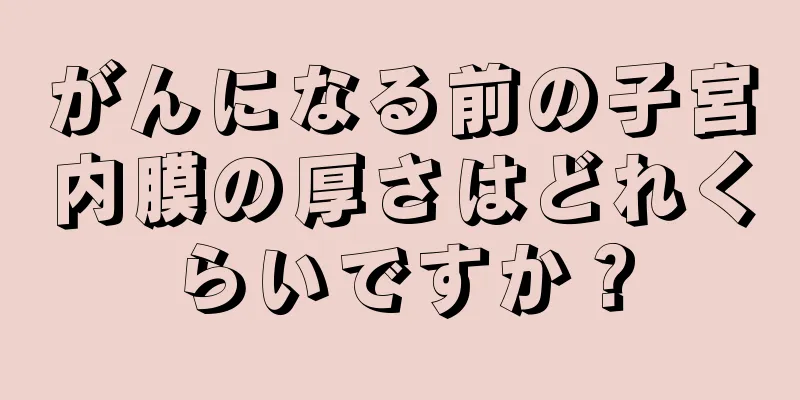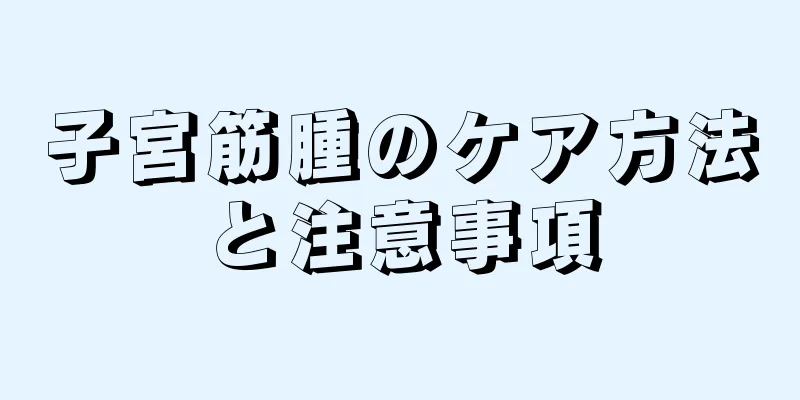血中脂質を下げる魔法の武器「オクラ水」が大人気! 3つの簡単なステップで糖尿病と関節痛を効果的に緩和
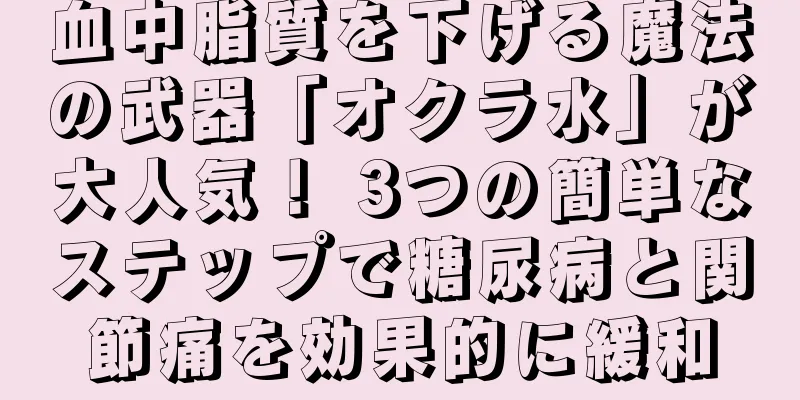
|
毎日一杯の「オクラ水」を飲むと、美肌効果だけでなく、糖尿病や高血圧、動脈硬化などの慢性疾患の改善にも効果が期待できます。以下では、V編集部が「オクラ水」の作り方や飲む際のQ&Aをまとめました。 日本人が「緑の高麗人参」と呼ぶオクラには、亜鉛やセレンなどの微量元素、ビタミンC、水溶性食物繊維が豊富に含まれています。定期的に摂取すると、消化を助け、肌を美しくすることができます。それだけでなく、日本の医師である市橋健一氏は、「オクラ水」を毎日飲むと、便秘が改善され、浮腫が解消され、糖尿病、高血圧、動脈硬化などの慢性疾患の緩和効果があることを発見しました。以下では、「オクラ水」の作り方と「最も効果的な飲み方」をご紹介します。 (写真/VOGUE提供) 日本の医師も推奨!ナチュラルダイエットセラピー[オクラウォーター] 「オクラ水」はオクラを一晩水に浸して作ります。これを飲むと毛細血管の血流が促進され、血糖値が下がり、糖尿病による動脈硬化や慢性関節痛が改善されます。食物繊維が豊富なので便秘やむくみの予防にもなり、健康に良い食事療法です。オクラ自体は食品なので、薬のような副作用はほとんどなく、誰でも安心して摂取できることから、天然のサプリメントとしても注目されています。 (写真/VOGUE提供) 日本の医師である市橋健一氏も、新著『オクラ水の奇跡の健康法』の中で、オクラ水を飲むと糖尿病、高血圧、動脈硬化、脂質異常症、膝痛、腰痛、脊柱管狭窄症、下肢静脈瘤、めまい、悪臭皮膚炎、逆流性食道炎、五十肩、腎機能障害、便秘などの症状が改善されることが医学的報告で確認されていると指摘している。この自然で簡単に作れる栄養補助食品に魅力を感じますか?以下は「オクラ水」の作り方です。 (写真/VOGUE提供) 「オクラ+水=天然の滋養強壮剤」健康を守る栄養配合 【材料】 生オクラ5本(国産または他産地産)、水100~180ml (写真/VOGUE提供) 【ステップ】 1.オクラの茎を取り除く 2.ステップ 1 のオクラを、切った面を下にしてボトルまたはカップに入れ、オクラが浸るくらいの水を加えます。 3.蓋またはラップで覆い、冷蔵庫で約8〜12時間冷やします。オクラを取り出して飲む ヒント農薬が気になる場合は、使用前に丁寧に洗うか、水に30分ほど浸してからご使用ください。オクラは水に浸して調理して食べることができます。ただし、水に浸した後24時間以内であれば、再びオクラ水を作ることができます。 (写真/VOGUE提供) 【オクラウォーター】の飲み方 毎朝、食前または食後にオクラ水を1~2杯飲み、24時間以内に飲み切ってください。オクラ水は冷やして、または常温で飲んだり、温水に加えて飲んだりすることができます。ただし、冷凍したり加熱したりすることはできません。飲み込みにくい場合は、黒酢、だし、メープルシロップ、オリゴ糖などを加えて味を整えてからお飲みください。 (写真/VOGUE提供) [オクラ水]に関するよくある質問4つ Q1. 朝にオクラ水を飲まなければなりませんか? A: 「朝に飲むのが良いですよ。」オクラは8時間以上水に浸す必要があるため、夜に浸しておけば翌朝起きたときに飲むことができます。ただし、オクラ水は朝に飲む必要はありません。食前や食後に飲んでも同じ効果があります。血糖値の上昇を緩やかにしたい場合は食前に、睡眠中の足のつりを防ぎたい場合は就寝前に飲むなど、目的に合わせて飲む時間を調整できます! Q2. オクラの水はなぜ加熱したり冷凍したりできないのですか? A: 「酵素の働きが関係しているのかもしれません。」オクラ水には他にどのような有効成分が含まれているかはまだ不明ですが、酵素が重要な要素の一つではないかと推測されています。酵素の活性は35~45℃で最も高くなります。凍結状態では酵素は働かず、高温になると酵素の活性が失われます。 (写真/VOGUE提供) Q3.オクラ水の効果的な飲み方は他にもありますか? A:オクラをルイボスティーに浸して飲むと、毛細血管の詰まりを防ぎ、微小循環の流れを改善できます。 「ルイボスティー」は、微小血管内の鉄2物質を活性化し、微小血管細胞を強化することができるからです。オクラを浸すのに使った水を、室温まで冷ました南アフリカ産のお茶に置き換えるだけです。お茶の風味で料理の味を忘れて食べやすくなります。 Q4. オクラ水をもっと美味しくするにはどうすればいいですか? A: 「黒酢、アフリカ国宝茶、だし汁、メープルシロップ、オリゴ糖、羅漢果エキス、レモン、グレープフルーツ等」を加えます。アイスでも美味しいですが、アイスで飲みたくない場合はぬるま湯(体温くらいで大丈夫です。温めすぎると酵素が失活します)を注いで飲んでも大丈夫です。なお、砂糖やカフェイン、乳製品を含む飲み物は交感神経を興奮させ、血流を悪くする原因となるので、一緒に飲まないように注意してください。また、物理的差異のため、蜂蜜やリンゴ酢は推奨されません。 (写真/VOGUE提供) 出典:長昌生活文化創意「オクラ水奇跡の健康法」/著者:市橋健一 ※この記事はVOGUE誌の許可を得て掲載しており、無断転載を禁じます。 (記事全文はVOGUE.comをご覧ください) ベッドに横になっているだけで痩せられます!毎日寝る前に5分間の[全身痩身エクササイズ]で、引き締まったお尻、ほっそりとした脚、そして細いお腹を同時に手に入れることができます これをやって免疫力を高めましょう!毎日できる健康増進法10選 「満腹の60%までしか食べず、フルーツは朝だけ食べましょう。」ティファニー・スーが、美しい体型を維持するための[重要な秘密]を伝授 お腹とウエストを細くするエクササイズ:片足の犬のポーズのバリエーション、片足でひざまずいてツイストするポーズ、2つの動きを連続して行う、お腹を細くして腹筋を鍛えるヨガ、とても効果的 さらに興味深いレポートはVOGUEのウェブサイトをご覧ください。 ※この記事はVOGUE誌の許可を得て掲載しており、無断転載を禁じます。 |
<<: 【動画版】肝臓をスッキリ元気に!脂肪肝を解消する必須の脂肪減少茶2選
>>: HIIT(高強度インターバルトレーニング)は短期間で筋肉を鍛えるのに役立ちますか?日本の医師が神話を払拭
推薦する
先天性膣欠損症の治療方法
先天性膣欠損症はどのように治療すればよいのでしょうか?先天性膣欠損症の外科的治療は、主に尿道、膀胱、...
冬のドリンク温まりトラップ! ?寒い季節の食べ物に関する2つの大きな誤解を払拭する
プロの栄養士:高繊維豆乳を温めて飲むのが「セルフウォーミングダイエット」をマスターする秘訣寒風の中、...
病理学では子宮内膜の厚さはどの程度になるのでしょうか?
子宮内膜肥厚病理学では何が見つかりますか?病理学は通常、病理学的検査を指します。子宮内膜の厚さの病理...
月経困難症には鎮痛剤だけを服用すればよいのでしょうか?子宮の冷えが原因でしょうか?
月経困難症は必ずしも子宮の冷えが原因で起こるわけではありません。鎮痛剤は痛みを和らげる短期的な手段に...
有酸素運動は心肺機能に良いだけでなく、意外なメリットもあります。
近年、エクササイズが流行していますが、スポーツの種類は数百種類あります。心肺機能を強化するためには、...
付属器炎の症状
付属器炎には、急性付属器炎と慢性付属器炎という 2 つの主要なカテゴリがあります。付属器炎の種類によ...
子宮脱の手術方法
子宮脱の手術方法:子宮脱:子宮脱は女性によく見られる生理的疾患です。これは、子宮が通常の位置から膣に...
専門家が付属器炎の初期症状を説明
生涯にわたって付属器炎の発症率は増加していますが、ほとんどの女性は付属器炎についてあまり知らず、それ...
満腹感を高め、むくみを軽減します!大豆おから料理3品の作り方
健康維持のトレンドが広まるにつれ、自宅で豆乳を作る人が増えています。しかし、煮立った後に残った豆乳を...
重度の子宮頸部びらんをどのように診断し、治療するのでしょうか?重度の子宮頸部びらんの診断と治療に関する専門家のアドバイスを聞く
重度の子宮頸部びらんにはどうすればいいですか?多くの女性の友人は、終わりのない痛みと苦痛をもたらす子...
子宮筋腫の治療にどのような薬を服用すべきか
子宮筋腫の薬物治療では通常、ゴナドトロピン放出ホルモン作動薬 GnRH-a、プロゲステロン受容体調節...
子宮筋腫の患者はどんな果物を食べるべきでしょうか?子宮筋腫のある女性は3種類の果物を食べなければならない
子宮筋腫の患者は、水分と栄養を補給するために、日常生活でより多くの果物を食べる必要があります。果物に...
子宮内膜ポリープのせいで月経が長引いてしまったらどうすればいいですか?
子宮内膜ポリープのせいで月経が長引いてしまったらどうすればいいですか?子宮内膜ポリープによる月経は、...
子宮頸部のイボを早期に診断する方法
子宮頸部イボは数え切れないほど多くの患者に精神的にも肉体的にも大きな害を与えてきました。症状が重篤な...
痩せている人でもメタボリックシンドロームになる可能性はありますか?メタボリックシンドロームの5つの診断基準と5つの予防のヒント
近年、食文化の変化に伴い、台湾の2017年から2020年までの「国家栄養健康変化調査」によると、太り...