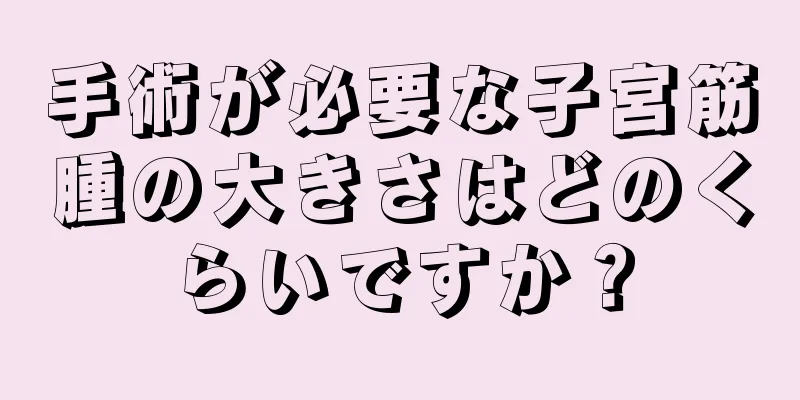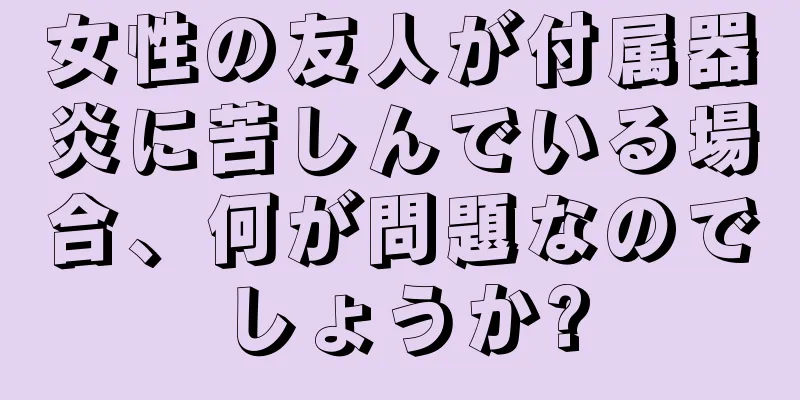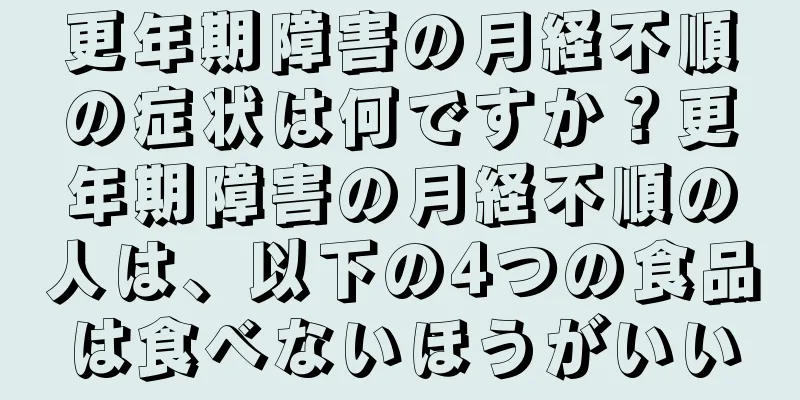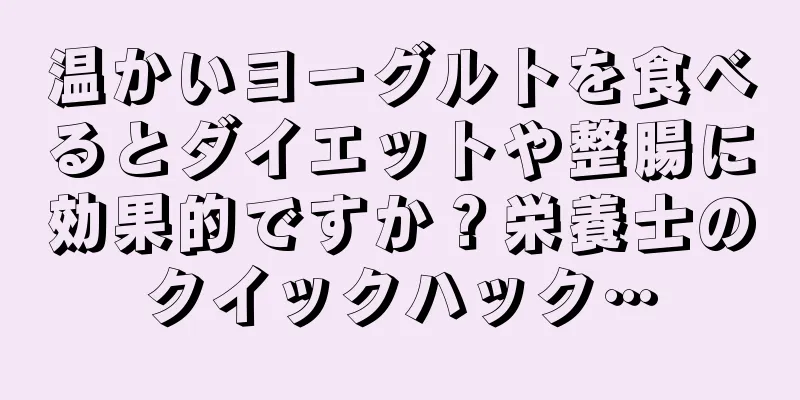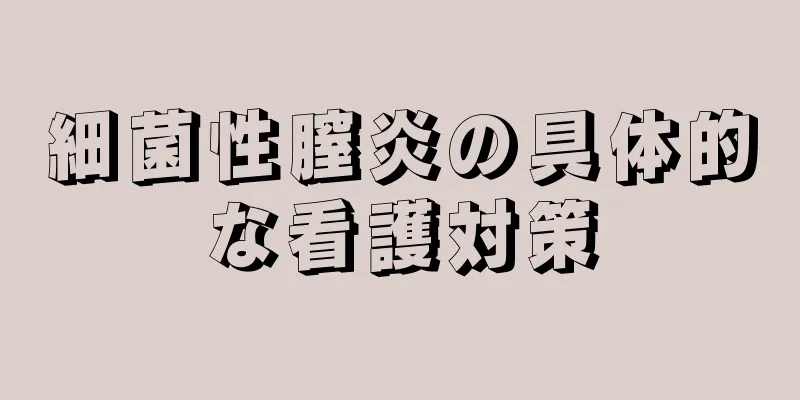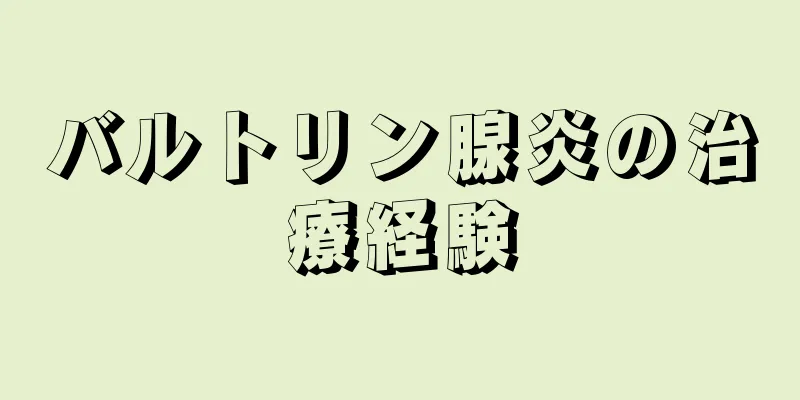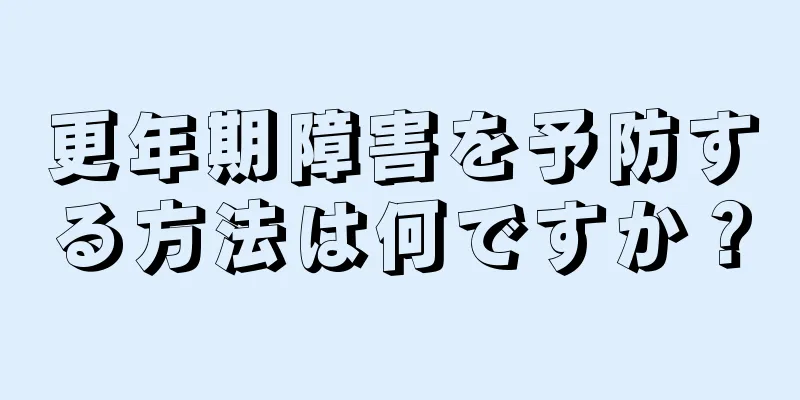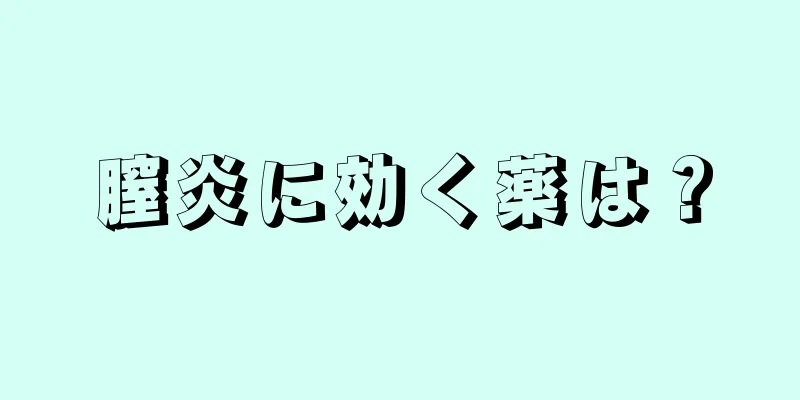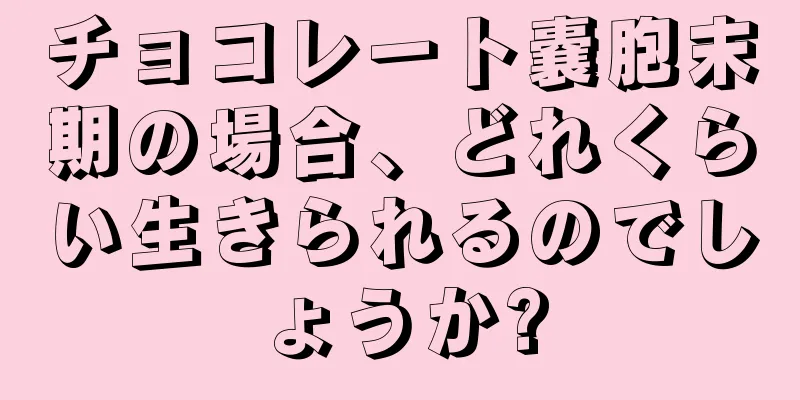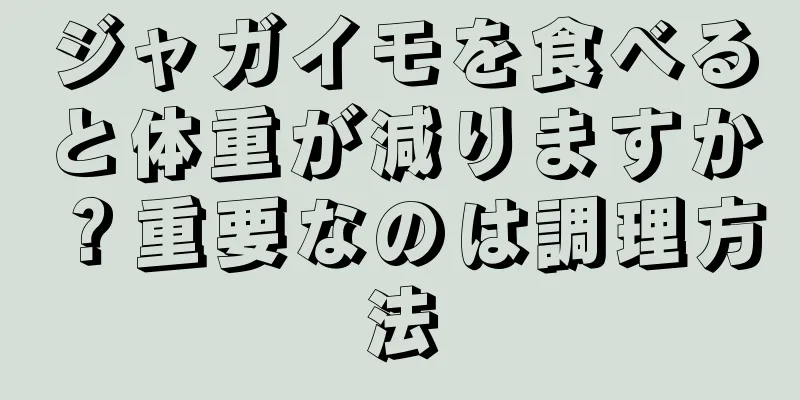「筋肉を増やし、脂肪を減らす」減量には別の食事が必要ですか?栄養士:偏食を避け、一度に食事目標を達成するには、「3つ選んで4つ減らす」ことを覚えておいてください
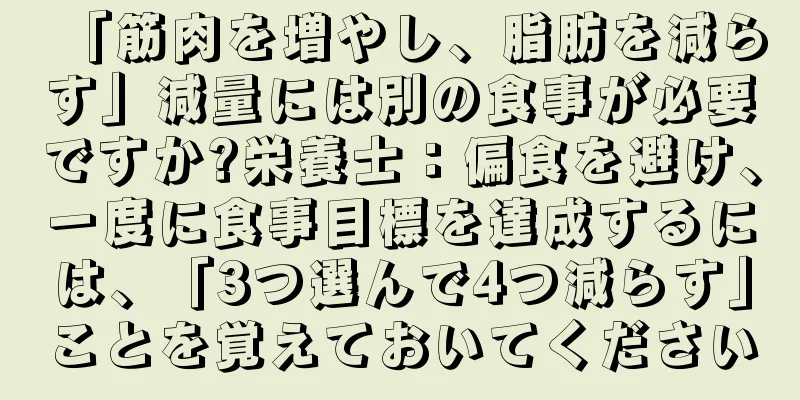
|
減量を試みている人なら、「食事70%、運動30%」という言葉を聞いたことがあるでしょう。これは、食事に注意を払うだけでなく、運動も減量には重要であることを意味します。運動は筋肉を増やし、脂肪を減らし、体を鍛えることができます。しかし、本当に「痩せている」ことを楽しみ、再び体重が増えないようにするには、どのように食生活をコントロールすればよいのでしょうか?栄養士は、半分の労力で2倍の結果を得るためには、「3つを選んで4つを減らす」という偏食の原則を心に留めておくべきだと私たちに思い出させます。 ダイエットといえば、誰もが「筋肉を増やして脂肪を減らす」ことを考えるでしょう。そして、そのためには「食事70%、運動30%」が必要であることも誰もが知っています。高い投資収益率を追求するなら、もちろん、まず7つのポイントを達成したいものです。食事制限に頼ると、体重はすぐに落ちますが、すぐにリバウンドし、まだ非常に空腹を感じ、生活が困難になります...」この「70%ダイエット」をどのように達成できるのでしょうか? 減量の第一歩は食べ物にこだわることです。筋肉をつけることと脂肪を減らすことは、2 つの異なるダイエットです。 林口長庚記念病院栄養療法科の栄養士、曽一新氏は、減量の第一歩は「食べ物にこだわること」を学ぶことだと語った。誰もが筋肉を増やし、同時に脂肪を減らしたいと願っている。体重を知ることに加えて、体組成も理解し、筋肉量を増やしたり体脂肪を減らしたりするために、個人のニーズに応じて「食べる」ことができるようにする必要がある。 「筋肉増強ダイエット」と「脂肪減少ダイエット」は異なるため、どちらもプロトタイピング食品と高タンパク質比率に基づいていますが、3大栄養素の構成比率は異なります(図1を参照)。筋肉を増やすには、炭水化物とタンパク質の比率(3〜4:1)を調整しながらウェイトトレーニングを組み合わせる必要がありますが、ウェイトトレーニングを行わない場合、食事だけでは筋肉量を維持することしかできません。脂肪を減らすには、総カロリーを厳密に制御し、炭水化物と脂肪の比率を減らす必要があります。 (写真提供:林口長庚記念病院) しかし、なぜ一部の人々は同時に筋肉を増やし、脂肪を減らすことができるのでしょうか?なぜなら、隠れ肥満(必ずしも太りすぎではないが、体脂肪が多く筋肉量が少ない人)の人は、いわゆる「サルコペニア肥満」だからです。食生活を変え、適度な運動をすれば、筋肉を増やし、同時に脂肪を減らすことができます。 栄養士の曽一新氏は、もともと体脂肪は高いが筋肉量が少ない人は、次の「3マイナス4」の原則に従い、「食べ物にこだわる」べきだと述べています。 【ピック3】 1. バランスの取れた栄養を選ぶ カロリーとタンパク質を計算するだけでなく、すべての食事はバランスが取れている必要があります。つまり、食事にはでんぷん、タンパク質、脂肪、果物、野菜が含まれている必要があります。意図的にでんぷんを避けないでください。特に、果物や野菜は、食物繊維、ビタミン、ミネラルなど、人間の脂肪代謝に重要な要素を提供します。同時に、水(体重1キログラムあたり1日30ml)は体に必要な重要な要素の1つです。 2. 栄養成分表示には気をつける 1. 材料を多い順と少ない順に並べ、砂糖と油が後から入っているものを選びます。 2. 1食あたりのカロリー量(カロリー量×総食数)は400~500kcalです。 3. トランス脂肪酸を避ける。 4. 1日の推奨ナトリウム摂取量は2400 mgを超えてはなりません。 3. 食べる順番を決める 澄んだスープまたは水→野菜→豆、魚、卵、肉→でんぷん。研究によると、同じ総量の食べ物でも、食事と一緒におかずを食べるという従来の順序を逆にして、野菜をご飯と一緒に食べると、食べ物による血糖値の上昇速度が下がり、血糖値とインスリンの上昇が緩やかになり、体脂肪が形成されにくくなることがわかっています。ただし、この食事の順番は胃潰瘍や胃食道逆流症の人には適していないので注意してください。 [マイナス4] 1. 精製糖の摂取を減らす 蜂蜜、黒砂糖、グラニュー糖、角砂糖、果糖、黒砂糖などの添加糖はすべて精製糖です。1日の推奨摂取量は総カロリー必要量の10%を超えてはなりません(5%未満が望ましい)。例えば、1日の総必要量が1200カロリーで、砂糖1グラムが約4カロリーに相当する場合、精製糖に換算すると30グラム(1200カロリー×10%÷4カロリー=30グラム)を超えてはならず、15グラム以下に抑えるのが望ましいです。 2. 余分な脂肪の摂取を減らす タンパク質を豊富に含む食品における飽和脂肪の割合は、低いものから高いものの順に、豆類 < 魚類 < 卵 < 肉類、その中でも白身肉 (魚類、鶏肉) < 赤身肉 (豚肉、牛肉、羊肉) です。すでに知られている揚げ物や動物の皮(鶏皮、アヒル皮、豚皮、豚足)などに加えて、サンドイッチの層にあるマヨネーズ、ゴマケーキのパイ生地の層、詰め物が入ったパイ生地のパン、火鍋の沙茶ソース、煮豚飯の煮豚、鉄板焼きの焼きそば、冷麺のゴマペースト、ルンニャンのピーナッツパウダーなど、私たちの食事に隠れた脂肪も見つける必要があります。 3. 塩分の過剰摂取を減らす 主観的に塩辛いと感じる調味料や漬物(キュウリの漬物など)のほか、隠れた高ナトリウム食品としては、ミートボール、魚団子、燕の巣団子、かまぼこ、トースト、クラッカーなどがあります。 4. 加工された赤身肉製品を減らす ホットドッグ、ソーセージ、肉詰め、ジャーキー、ベーコン、ハムなど、風味を高め、保存期間を延ばすために塩漬け、漬け込み、発酵、燻製などの加工が施された肉。 筋肉を増やして脂肪を減らすために外食する人のための食事の組み合わせの例(表1参照) (写真提供:林口長庚記念病院) 栄養士の曽一新氏は最後に、外食する人は食事を選ぶときに「3つ選んで4つ引く」という原則を覚えておくべきだと注意を促した。たとえコンビニの食べ物を選んだとしても、塩分が多いことに注意する必要がある。そのため、栄養と利便性のバランスをとるには、毎食違う店で食べるのがベストだ。 |
<<: ある若い女性は、体重を減らすために緑の野菜とゆで卵だけを食べましたが、ひどい抜け毛に悩まされました... 栄養士:健康的に体重を減らすための4つの食事原則
>>: 夏はメロンを食べると涼しくなります。冬メロンは熱を逃がし、ダイエットにも役立ちます。栄養士:冬瓜の種を茹でて水を飲むと体内の老廃物を排出しやすくなります
推薦する
子宮筋腫は通常何歳で発症しますか?子宮筋腫はどの年齢層で発生しますか?
子宮筋腫は通常何歳で発症しますか?子宮筋腫はどの年齢層で発生しますか?子宮筋腫は子宮の筋層で増殖する...
子宮内膜結核の看護対策
子宮内膜結核は現在多くの女性によく見られます。また、治療が難しい病気でもあります。多くの場合、治療効...
卵巣嚢胞の主な検査は何ですか?
卵巣嚢胞の検査 卵巣嚢胞の検査の主な側面は何ですか?このような問題の場合、卵巣嚢胞には一般的に医師の...
一般的な無痛中絶の利点をご紹介します
中絶による被害を最小限に抑えるために、予期せぬ妊娠をした多くの女性の友人は、無痛中絶を選択し、痛みを...
専門家が子宮頸管炎の重要な原因を解説
子宮頸管炎は、女性、特に以前に他の子宮頸管疾患を患ったことがある女性に非常によく見られる婦人科疾患で...
子宮頸炎は遺伝しますか?
子宮頸炎は遺伝しますか?現在、子宮頸炎の患者の多くは、自分の病気が子供に遺伝することを心配し、早めに...
月経不順の主な原因は何ですか?
10代の少女の月経不順の主な原因は何ですか? 10代の少女の月経不順も、一般的な婦人科疾患の1つで...
中絶後の二次子宮掻爬術の危険性は何ですか?
妊娠初期には流産がよく起こる現象です。女性が誤って転倒したり、流産したりすると、胎児の健康に重大な影...
続発性無月経とは
続発性無月経とは何ですか?続発性無月経とは、女性は定期的に月経があるものの、何らかの病的な理由により...
子宮筋腫ができると、体にどのような変化が起こりますか?
どのような病気にも症状があり、それがどんな病気なのかを警告し、診断の基準として役立ちます。では、子宮...
更年期障害の診断
更年期障害の診断根拠については積極的に把握する必要がある。更年期障害の診断根拠を正しく把握することに...
女性は子宮頸部びらんや不妊症をどのように治療するのでしょうか? 3つの主要な治療法が子宮頸部びらんと不妊症を効果的に治療する
子宮頸部びらんは、女性によく見られる子宮頸部の病気の一つであり、女性不妊の原因の一つでもあります。こ...
急性骨盤内炎症性疾患は頻尿や排尿時の痛みを引き起こしますか?
人工妊娠中絶の際の無菌操作が厳格でないと骨盤内炎症性疾患が発生する可能性があり、骨盤内炎症性疾患は慢...
先天性膣欠損症の治療
膣器系胚の先天性欠損は、発育中に内的または外的要因によって妨げられる場合や、遺伝子変異(家族歴がある...
子宮奇形による流産の確率は高いですか?
子宮奇形は流産のリスクを高める可能性があり、これは胎児が成長する環境への影響と関係しています。子宮奇...