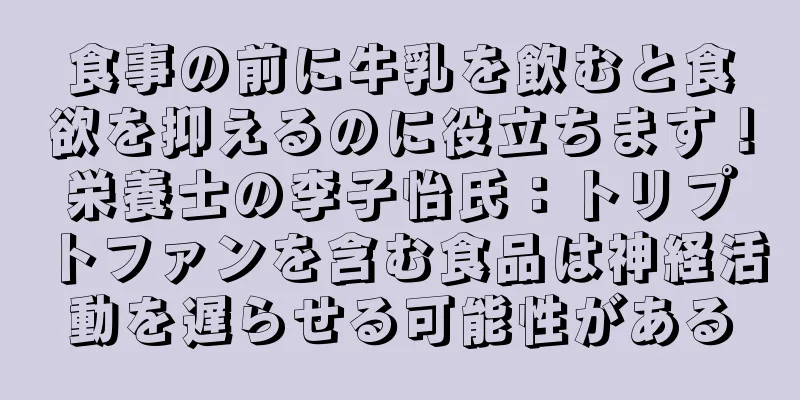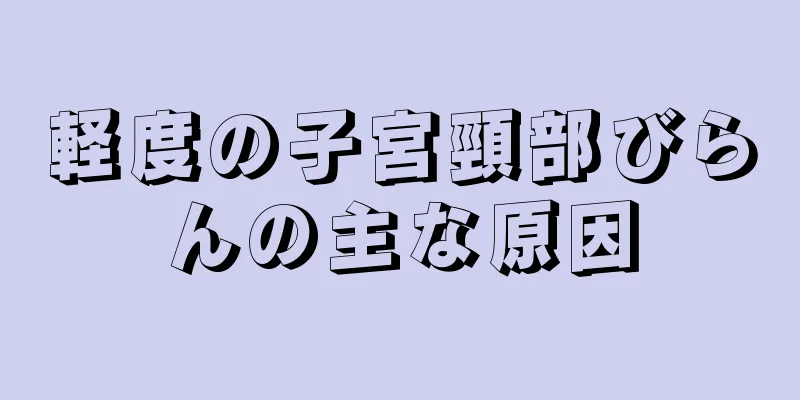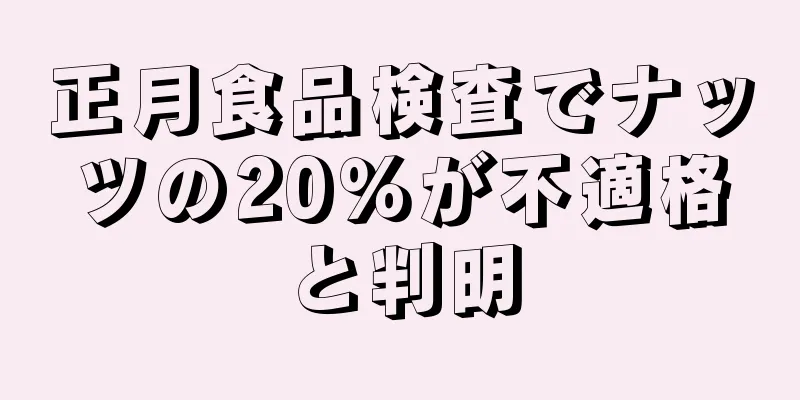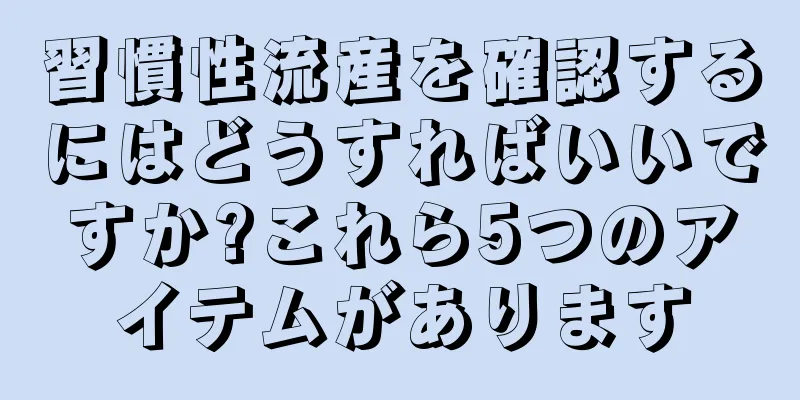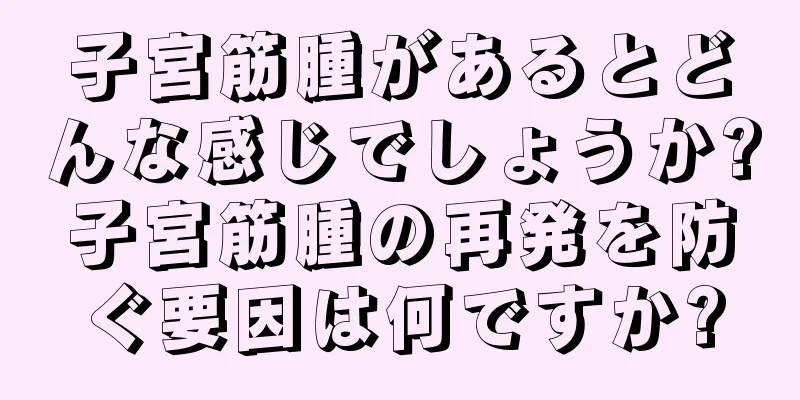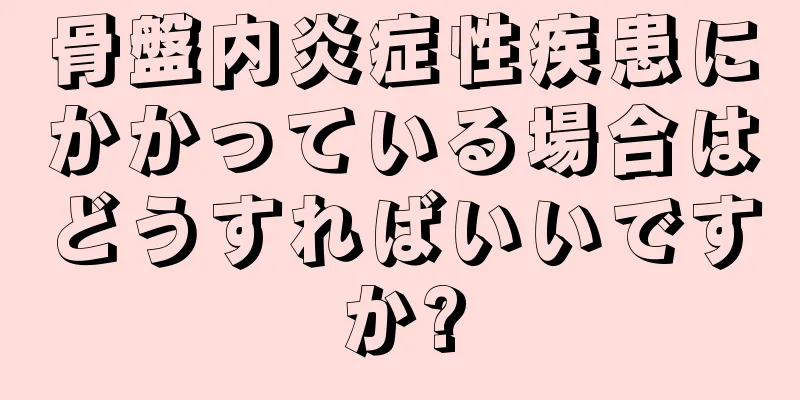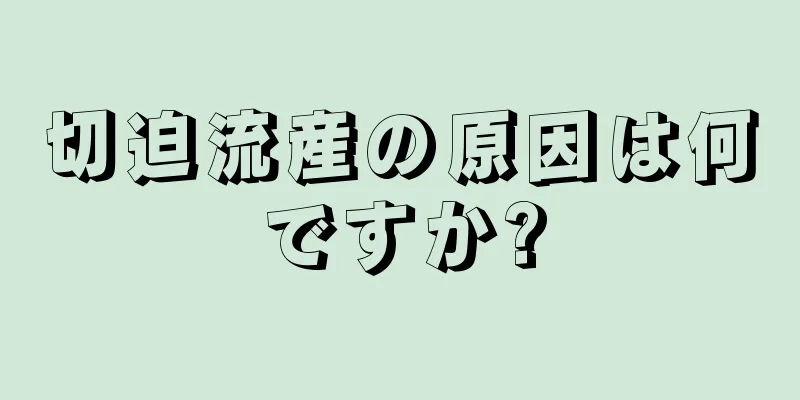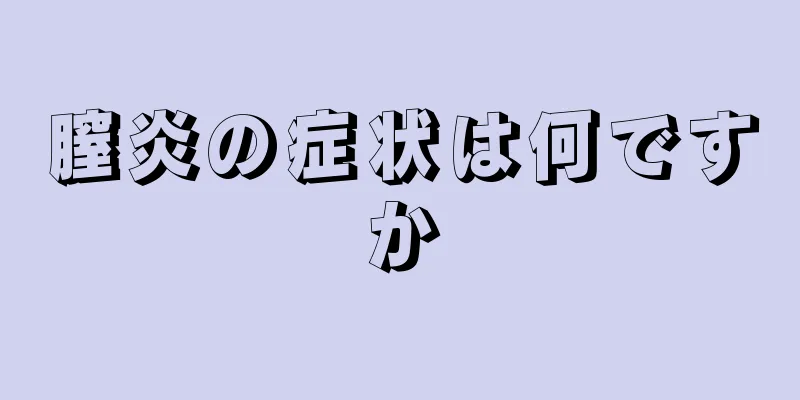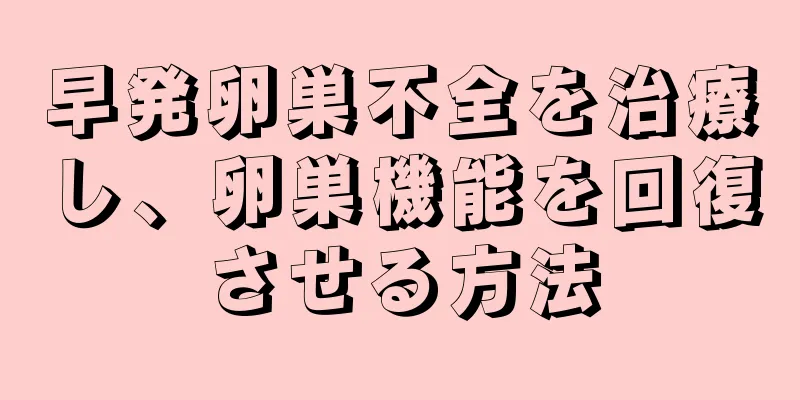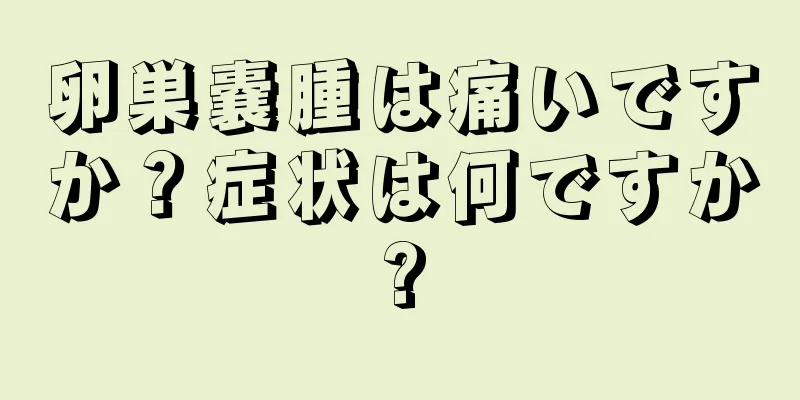火鍋カロリーランキング:辛い火鍋が1800カロリー以上で1位

|
鍋料理が好きな方はぜひ写真を撮ってくださいね!どの種類の鍋を食べるか決める前に、まずはさまざまな鍋のカロリーを知っておく必要があります。調査によると、鍋のカロリートップ5は、1位が辛い鍋で、1食あたり約1,800カロリー、2位がザワークラウトと豚肉の鍋で、1食あたり約600カロリー、3位が羊肉の鍋で、1食あたり約500カロリーです。週に2回以上食べると、蓄積されたカロリーが非常に心配になります。運動不足と相まって、時間が経つにつれて体内に蓄積され、除去するのが難しい頑固な脂肪が形成されます。 辛い鍋一食あたりのカロリーは1,800カロリーにもなり、かなり驚きます。 火鍋はなぜカロリーが高いのでしょうか?健康的に食べることは可能でしょうか?栄鑫医院の栄養士、陳雲帆氏は、火鍋の主なカロリー源はスープベースであり、特に辛い火鍋は脂肪とカロリーが高いと述べた。まずは浮いた油を取り除くことをお勧めします。面倒な場合は、かつお節、カレイ、トウモロコシ、昆布、キャベツ、キノコなどの低脂肪食材を使って調理すると、スープの美味しさを損なわずにカロリーを抑えることができます。鶏骨スープや豚骨スープを使って火鍋のスープベースを作る場合、カロリーは辛い火鍋よりはるかに低くなりますが、それでも一杯あたり約40〜50カロリー含まれており、無視できない量です。 次に、鍋の材料を検討する必要があります。新鮮な食材を選び、加工品をあまり使わないのがベストです。新鮮な食材は余分な脂肪を含まないため、一般的にカロリーが低くなります。カキ、アサリ、エビ、イカなどの魚介類は、同じ量の肉に比べてカロリーがはるかに低く、肉の一部を置き換えることができるため、肉は適度に使用する必要があります。葉野菜やキノコなどの野菜はカロリーが低いので、肉よりも先に食べることができます。こうすることで、まず満腹感が得られ、その後自然にその後の食材の摂取量を減らすことができます。ただし、野菜の中でもトウモロコシやサトイモはカロリーが高いので、食べる量には注意してください。こんにゃく春雨やこんにゃくイカなどのこんにゃく製品は、余分な味付けがなく、カロリーも低いので、試してみる価値があるのでおすすめです。 最後に、ディップソースは少なめにしてください。適切なディップソースは火鍋の味を増すことができますが、風味が増すと同時に、大量の脂肪の摂取も増加する可能性があります。沙茶ソース、ベジタリアン沙茶ソース、ゴマソースなどは、大さじ1杯あたり約100カロリーと、カロリーが低くありません。なお、つけダレとして使われる卵黄はコレステロール含有量が低いわけではないので、高脂血症の患者は過剰摂取に気をつけなければなりません。 健康でハイになりましょう!今すぐいいねして《》のファンクラブに入会しましょう! |
<<: おせち料理にクレイジーな整形手術!餅と大根餅がヘルシーな鍋に変身
>>: 鍋を食べるときはアルコールペーストを使用しないでください。高濃度のメタノールには注意してください。
推薦する
2度の頸部炎症に効く薬は何ですか?
子宮頸管炎2度に効く薬は何ですか?グレード 2 の頸部炎症は、セフトリアキソンナトリウム注射液、セフ...
骨盤内炎症性疾患の症状
骨盤内炎症性疾患は一般的な婦人科疾患です。では、女性の友人にとって、骨盤内炎症性疾患の典型的な症状は...
子宮内膜結核にはどんな薬を飲めばいいですか
現在、子宮内膜結核の最も一般的な治療法は薬物療法です。中医学と西洋医学の違いに基づいて、子宮内膜結核...
無月経に対する漢方茶療法
無月経は治療が難しく、治療に長い時間を要する病気です。では、無月経はどのように治療すればよいのでしょ...
子宮筋腫にはどんな薬を服用すればよいですか?子宮筋腫を除去するためにどのような漢方薬を服用すればよいでしょうか?
子宮筋腫は婦人科でよく見られる良性腫瘍です。悪性化することはありませんが、女性の生活に一定の支障をき...
中絶後にライチを食べても大丈夫ですか?
一般的に、中絶後は適度にライチを食べることができますが、腐ったりカビが生えたりしたライチは食べないよ...
涼しくなるためにスムージーを飲んでいますか?砂糖含有量はバブルミルク1カップ分
夏には涼をとるために冷たい飲み物が必要ですが、さわやかなフラペチーノスムージーには700ccのバブル...
子宮内膜肥厚の症状は何ですか?
人生において、子宮疾患にかかることを心配する女性は多いのですが、子宮疾患には起こりやすい種類がたくさ...
子宮頸部びらんの治療に最も権威のある病院はどこですか?
子宮頸部びらんの治療に最も権威のある病院はどこですか?婦人科の専門家は次のように注意を促しています。...
高プロラクチン血症を伴う妊娠の臨床看護
高プロラクチン血症を伴う妊娠の臨床ケアでは何に注意すべきでしょうか?高プロラクチン血症は、特に高プロ...
無痛中絶後に食べてはいけないものは何ですか?中絶後に健康を保つために何を食べるべきですか?
無痛中絶後に食べられないものは何ですか?中絶後に健康を維持するために何を食べたらいいでしょうか?無痛...
飢えずに体重を減らそう!簡単に体重を落とす栄養たっぷりのダイエット食5選
体重を減らしたい人にとって、空腹を感じることなく効果的に体重を減らす方法を知ることは非常に重要です。...
1年半後に再び閉経を迎えるのは普通ですか?原因分析と対策
最近、閉経後1年半で突然無月経になったという女性が多く報告されています。これは正常ですか?さまざまな...
子宮内膜結核の外科治療を行っている病院
子宮内膜結核の外科治療を行う病院の選び方は?子宮内膜結核は患者にとって非常に有害であるため、発見後は...
頸部肥大の食事タブー、頸部肥大
子宮頸部肥大は一般的な婦人科疾患です。患者は治療を受けるにあたって良い姿勢を保ち、日常の食生活に十分...